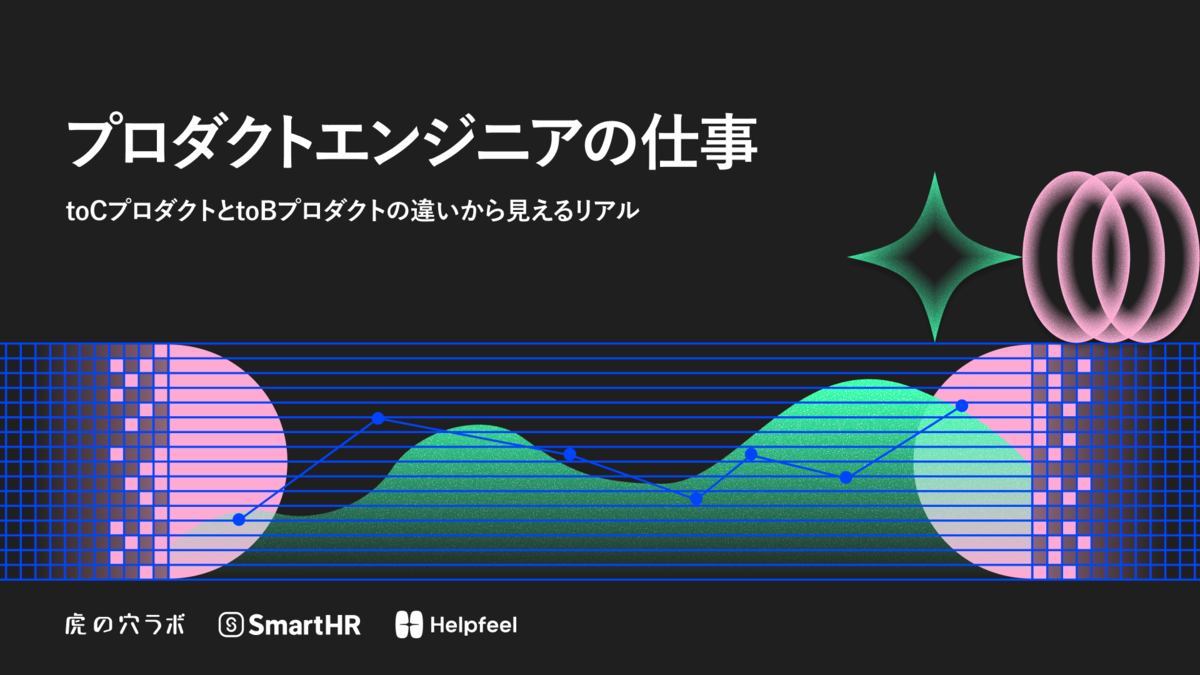
急に気温が下がってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか? オクタニです。
今回は、2025年 9月 25日に開催した「プロダクトエンジニアのお仕事 ~toCプロダクトとtoBプロダクトの違いから見えるリアル~」をレポートします。
イベント紹介
虎の穴ラボ、SmartHR、Helpfeelの3社による「プロダクトエンジニアのお仕事」についてトーク&パネルディスカッションを行うイベントです。
課題発見からプロジェクトの遂行までを一貫して対応する「プロダクトエンジニア」。
本イベントではtoCとtoBそれぞれのプロダクトの価値基準やスケジューリングの差など、異なるプロダクト特性から生まれるプロダクトエンジニアの仕事の違いについて具体的な思考法と実践術を共有します。
配信はアーカイブで視聴できます。
開催概要
| 時間 | 内容 | スピーカー |
|---|---|---|
| 19:00-19:30 | 受付 | |
| 19:30-19:35 | オープニングトーク | |
| 19:35-19:45 | ユーザーの「好き」に応えるプロダクト開発:私たちはなぜ「Why」を考えるか | 河野 裕隆 / 虎の穴ラボ株式会社 |
| 19:45-19:55 | BtoBプロダクト開発の深層:信頼性をエンジニアリングする旅路 | にしはら ちひろ / 株式会社SmartHR |
| 19:55-20:05 | Win - Win - Win を目指す:BtoBtoCプロダクトにおける価値の定義 | 田中 陽輔 / 株式会社Helpfeel |
| 20:05-20:15 | 休憩 | |
| 20:15-20:45 | パネルディスカッション | |
| 20:45-20:55 | closing | |
| 20:55-21:45 | 懇親会 |
セッションレポート
ユーザーの「好き」に応えるプロダクト開発:私たちはなぜ「Why」を考えるか 河野 裕隆 / 虎の穴ラボ株式会社
弊社エンジニアの登壇です。 「プロダクトエンジニア」を「ユーザーとプロダクトの間にあるブランドを創り、育むエンジニアである」と定義し、Creatiaを事例として「ブランド」を軸に話しました。
- ユーザーの回答は「How」に寄る傾向があり、プロダクトエンジニアとして「Why」に注目して「ブランド」に沿うものを提案することが必要
- ブランドイメージは、短期的なユーザー体験よりも優先される
など、CtoCのサービスとして、「サービスを好きになってもらう」ことを目指していることそのための価値判断について触れられていました。
BtoBプロダクト開発の深層:信頼性をエンジニアリングする旅路 にしはら ちひろ / 株式会社SmartHR
「良いプロダクトエンジニア」であるために、
- ユーザーの体験への想像
- ユーザーが言葉にできない課題 => 「声なき声」
を拾い上げ、プロダクトに反映させる視点が欠かせないとお話しされています。
しかし、日々の開発に追われる中で体系的にプロダクトに一つ一つの声を繋げていくことは難しく、 そのためにSmartHR ではCREユニットを立ち上げ運用しているということでした。
Win - Win - Win を目指す:BtoBtoCプロダクトにおける価値の定義 田中 陽輔 / 株式会社Helpfeel
BtoBtoCのSaaSとしてHelpfeelのプロダクト特性を軸にお話しされていました。
- Helpfeelでは開発起点が3つある
- 顧客要望起点
- 社内要望起点
- エンジニア起点
- Helpfeelは自己解決率を最大化するためのツールとして、それを解決するペインを解明し機能を考える
「ユーザーの自己解決率の最大化」を目的として、一見良さそうなアイデアでも「エンドユーザーの価値に寄与しなければ採用しない」といった判断軸についてお話しいただきました。
パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、登壇者相互に個人セッションの意見交換から始めました。
『ユーザーの「好き」に応えるプロダクト開発:私たちはなぜ「Why」を考えるか』 へ
- サービスの利用者としてお話しを伺えて嬉しかった。
- 「ブランド」の考え方については、toCの考え方はかなり違っていて興味深かった。
『BtoBプロダクト開発の深層:信頼性をエンジニアリングする旅路』 へ
- より専門的な領域が要請される昨今で、よりユーザーのためになることをやるにはどうすれば良いのか?という話を聞けてよかった。
- 企業規模が大きく、CRE以外にも様々な開発の軸があるだろうと気になった。
『Win - Win - Win を目指す:BtoBtoCプロダクトにおける価値の定義』へ
- プロダクト開発のスピード感や先見性が、個人開発文化と相まってHelpfeelらしさとして感じられた。
- 普段使わせていただいている中での、「ペイン」の考え方は通じるものがあると感じた。
続けて、プロダクトへ入り込みながらそのプロダクトの問題解決を進めるプロダクトエンジニアに 求められる人物像について話していきました。
- 既存プロダクトに似たようなものを再生産するのは作りやすい時代になっていて、熱量で独自性を打ち出していくことができるのは価値が高い。
- 立ち上げ期のパッションは間違いなく効いてくるが、サービス規模が大きくなってくるとロジカル寄りの思考が必要になってきている。
- AI利用により開発速度は向上しているので、「そのサービスを好きだから使ってもらえる」という目標を共有できる人だと嬉しい。
- プロダクトエンジニア採用の温度感と見極めは難しい。
- これまでどういった考え方でサービスに向き合ってきたか?、仕事についてどのくらい考えて実行してきたか?を自分の言葉にできること。
- なぜその機能を作るのか?というWhyを言語化できるような人
など興味深い話をいただきました。
これらはセッションの一部です。
続きは、ぜひ動画でご覧ください。
まとめ
「プロダクトエンジニアのお仕事」の内容について簡単ですがレポートしました。
CtoC、BtoB、BtoBtoCという3つの立場で、「プロダクトエンジニア」の考え方や価値判断を共有し、考えを深めることができた会となりました。
私も懇親会に参加をしていましたが、サービスの課題の考え方や、ユーザーの意見の拾い上げ方についてお話しされている方が見受けられました。
採用情報
虎の穴では一緒に働く仲間を募集中です!
この記事を読んで、興味を持っていただけた方はぜひ弊社の採用情報をご覧下さい。
カジュアル面談やエンジニア向けイベントも随時開催中です。ぜひチェックしてみてください。 toranoana-lab.co.jp
